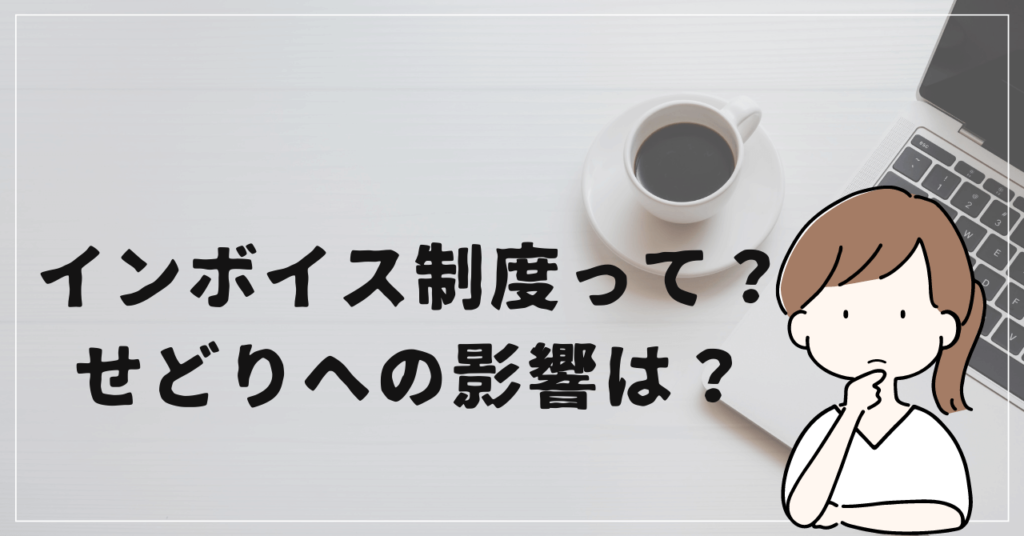
消費税の新しい制度として、2023年10月1日からインボイス制度が開始されます!「インボイス制度?聞いたことないな?」と思った方もいるかもしれませんが、インボイス制度は、消費税の課税事業者・免税事業者に関係なく、全ての事業者に影響を与える制度です。
現在せどり・転売ビジネスをしている方も、10月からこの制度に対応する必要があります。
でも、インボイス制度とは具体的にどのようなものなのか、どんな影響があるのか、今ひとつわからないという方もいますよね。
そこで今回は、こちらの内容を教えます。
- インボイス制度ってどんな制度?
- インボイス制度が影響を及ぼす事業者とは?
- せどりにおけるインボイスのメリットとデメリットって?
- せどり個人事業主はどんな選択をするべき?
 佐野
佐野インボイス制度の内容、せどりへの影響について一緒に学んでいきましょう!
利益商品が見つかりやすい店舗&リサーチ方法
「利益商品が全然見つかりません」「どこから商品を仕入れれば良いんですか?」という悩み相談をよく受けます。あなたも同じような悩みを抱えているかもしれませんね。
そんなあなたに、初心者でも利益商品が見つけやすい店舗を教えます。さらに、どうやれば商品が見つかるのかも具体的に教えていきます。
普段の買い物ついでに利益商品をゲットすることも可能なので、ぜひ学んでくださいね。
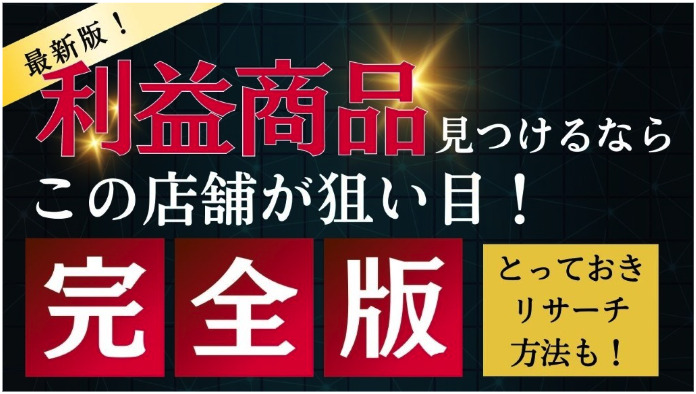
 無料でノウハウを手に入れる
無料でノウハウを手に入れるインボイス制度とは?

この制度導入された後は、国が定める記載事項をすべて満たしたインボイス(適格請求書)という書類を売り手が買い手に発行します。
この適格請求書(インボイス)が消費税を支払ったという証明となります。
2023年10月以降に消費税の仕入税額控除を申請する場合には、領収書に代わりインボイス(適格請求書)が必要です。
インボイス(適格請求書)がないと、仕入税額控除を受けられなくなってしまうので、ダブルで消費税を支払わないといけないことになり、売上が落ちてしまいます。
そのため、今後はインボイス(適格請求書)を発行できる課税事業者に取引がシフトし、個人事業主など免税事業者には不利になってしまうことが危惧されています。
以下の3つのポイントをしっかり押さえましょう。
- 2023年10月以降は、消費税の控除を申請する時にはインボイス(適格請求書)が必要となる。
- 消費税の証明のために、これまで領収書だけでよかった取引先が、インボイスの提出を求めることが考えられる。
- インボイスを出せない非課税の事業者の場合、インボイスを提供できる事業者(課税対象の事業者)ではないと、取引が拒否されるリスクがある。
インボイスとインボイス制度の違いは?
ここまで、「インボイス」と「インボイス制度」という2つの単語が出てきました。
いったん整理しましょう。
- インボイスとは
インボイスとは適格請求書と呼ばれる書類の事です。
売手が買手に対して正しい消費税の金額や率を伝える為の書類の事をあらわします。 - インボイス制度とは
この新制度は、法的な制度で別名「適格請求書等保存制度」とも呼ばれます。
適格請求書(インボイス)の交付と保存により、売手、買手間で消費税の仕入税額控除が適用されるという制度です。
インボイス制度を改めてシンプルに表現すると、「国が定めた請求書や納品書などに、インボイス(適格請求書)に必要な内容を記載すれば、仕入れにかかる税金を控除出来る制度」だということになります。
2023年10月1日からは、仕入れにかかった税金の控除を受けたい場合、インボイス制度に対応していく必要があります。
インボイスとインボイス制度。
意味がそれぞれ違うので、しっかり違いを理解しておいてくださいね。
インボイスの内容を理解し、適切に活用することで、税務の手続きや経理処理をスムーズに行うことができます。
また、税務に対してインボイス制度をより効果的に活用するためには、税理士や会計士のアドバイスを受けることも重要です。
最近は手頃な値段でアドバイスサービスを受けられるようになってきたので、ぜひ利用してみてください。
消費税の仕入税額控除って何?
インボイス制度を利用することで受けられるメリットとして消費税の仕入れ税額控除をあげましたが、具体的にどのような仕組みかも理解しておきましょう。
せどりビジネスを行なっている方はすでに馴染みがあるかもしれませんが、インボイス制度に深く関わることでもあるので、この機会に理解を新たにしておいてください。
「消費税の仕入れ税額控除」というのは、事業者が仕入のときに支払った消費税の金額を、あとで納める予定の消費税から控除できる制度のことをさします。
事業者が商品を仕入れる場合、その商品の価格には消費税が含まれています。
その商品を事業者が別の買い手に売却した場合、その事業者は国に消費税をおさめなければなりません。
しかし、仕入れの時点で既に消費税分を売値に上乗せて払っているため、このままでは事業者が二重に消費税を支払うことになってしまいます。
これを解消するのが、「消費税の仕入れ税額控除」なのです。
具体的な例で見てみましょう。
あなたはAmazonから10,000円の商品を仕入れました。
この場合、税率10%なので、あなたは「売値10,000円+消費税1,000円=11,000円」を支払うことになります。
次に、その商品を15,000円で他の人に売却したとしましょう。
その場合、「売値15,000円+消費税1,500円=16,500円」があなたの手元に入りますね。
あなたは商品を売った側の事業者として、この消費税1,500円を国に収める必要があります。
しかし、既に仕入れの時点で消費税1,000円を払っているため、このままだと二重に消費税を納めることになってしまいます。
そんな事態を防ぐために、「消費税の仕入れ税額控除」がつかえるのです。
これにより、仕入れ時点の消費税1,000円は払わなくて済むことになります。
売却時の消費税1,500円から仕入れ時の消費税1,000円を引いた500円のみを国に納めればいいので、グッと負担を減らすことができます。
「消費税の仕入れ税額控除」はこのように売上を大きく左右する要因です。
インボイス制度が大きく取り沙汰されているのは、インボイスがあるかないかで消費税控除の適用が左右されるからなのです。
インボイス制度で影響を受ける事業者
 では、インボイス制度は具体的にせどりにどんな影響をあたえるのでしょうか?
では、インボイス制度は具体的にせどりにどんな影響をあたえるのでしょうか?
特に免税事業者の場合、もしかしたら売り上げが下がってしまうかもしれません。
事業者の違いから説明していきましょう。
『免税事業者』と『課税事業者』の違いを理解しましょう
個人事業主には「免税事業者」と「課税事業者」という2つのカテゴリーに分けられます。
まず免税事業者は、その課税期間における課税売上高が1,000万円を下回る事業者で、納税義務が免除されます。
ただし、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。
課税事業者は消費税を納税する義務があります。
ですが調整対象固定資産の仕入れ等を行うことで還付を受けることもできます。
そして課税事業者の登録をする為には、納税地の所轄税務署長に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
せどりをすると、商品を仕入れて転売した時の利益(差益)がうまれます。
こ
の利益には消費税がかかりますが、「免税事業者」と「課税事業者」のどちらなのかによって、その後の取り扱いが異なってきます。
- 年間の税売上が1,000万円以下の場合、消費税を支払う義務がない
- 売上で得られた消費税を利益として取り扱える
- 課税事業者は商品を仕入れてから再販売で収益が上がった場合、消費税を支払わなければならない
- 納める金額は、仕入れ時の消費税金額を引いた分
これらの様に事業者は「免税事業者」と「課税事業者」のどちらかに分類されます。
課税事業者は消費税を納め、免税事業者は一定条件を満たせば消費税の納税義務が必要ありません。
ですが免税事業者はインボイス(適格請求書)を交付することができません。
インボイスがないと、仕入れた側は消費税の控除申請をすることができなくなってしまうので、結果的に免税事業者を使わなくなるのではないかと危惧されています。
インボイス制度は免税事業者にとっては不利だと考えられている理由はこの点です。
次からは、インボイス制度のせどりに対するメリットとデメリットを解説していきます。
せどりにおけるインボイスのメリットとデメリット
インボイス制度はせどりをするのにメリットはあるんですか? この制度により、せどりにも様々な影響が出ることが予想されます。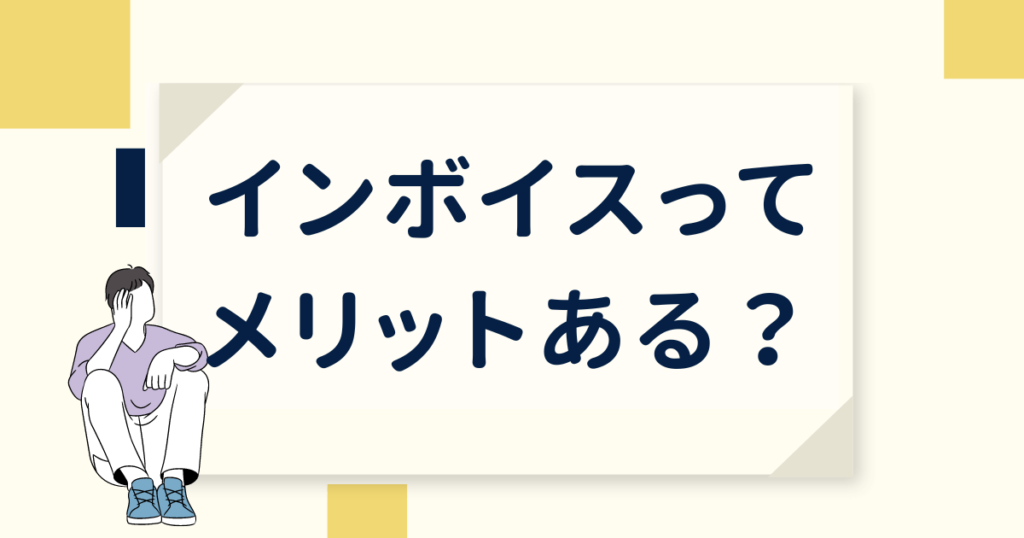

 佐野
佐野
次はそのメリットとデメリットをご紹介します。
インボイス制度のメリット
- 税務調査リスクを減らせる
インボイス制度を適用することで、税務調査時のリスクを低減することができます。
適格請求書を利用することで、税務署とのやり取りがスムーズになります。 - 取引の信頼性向上
インボイスを発行することで、取引先との信頼関係を築くことができます。
税務署への申請に必要な情報が揃っているため、相手側に喜ばれ、信頼性が上がることが予想されます。 - 事業の拡大
インボイスを発行することで、課税事業者としての取引上のメリットを享受することができます。
消費税を控除することができるため、収益を最大化することが可能です。
インボイス制度のデメリット
- 仕入れ控除の制約
仕入れに免税事業者を仕入れに利用している場合、インボイス(適格請求書)を出してもらうことができないので、仕入税額控除を利用することができなくなります。
このため、せどりを行っている個人事業主は取引先を適格請求書を発行してくれる事業者に変更する必要があります。 - 免税事業者との取引の変化
先ほどのべたように免税事業者とは、1年間の課税売上が1,000万円以下の事業者を指します。
インボイス制度がはじまると、免税事業者との取引した場合に不都合が生じることがあります。 - 免税事業者からの仕入れに頼っているせどり業者にとっては、取引の減少や廃業のリスクが懸念されます。
免税事業者との間で取引を行ってもインボイスを発行してくれません。
インボイス制度の導入後は、仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を行う業者が増加するだろうと予測されています。
その一方で免税事業者のまませどりビジネスを続ける場合は、インボイスを発行することが出来ないので、取引先の企業から契約を解除されたり、契約内容の変更を求められたりする可能性があります。
結果売り上げが下がってしまうかもしれません。
免税事業者が取引を断られて売上が下がってしまうと困ってしまいますよね。 佐野
佐野
そのため、せどりを行っている個人事業主は、仕入先を適格請求書を発行してくれる事業者に変更する必要があります。
この切りかえによって、取引が円滑になったり、税金の管理が簡単になったりするというメリットがあります。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、インボイス制度に適切に対応することが重要です。
現在のせどりの方法や取引先との関係を見直し、適格請求書を発行してくれる事業者との取引に切り替えることで、スムーズな経営を行うことができるでしょう。
Amazonをよく利用するせどり業者は適格請求書発行事業者になるという選択が必要かもですね。
 佐野
佐野次に、あなたが仕入れ元の場合どのような対応が必要になるかをみていきましょう
免税事業者と課税事業者の選択
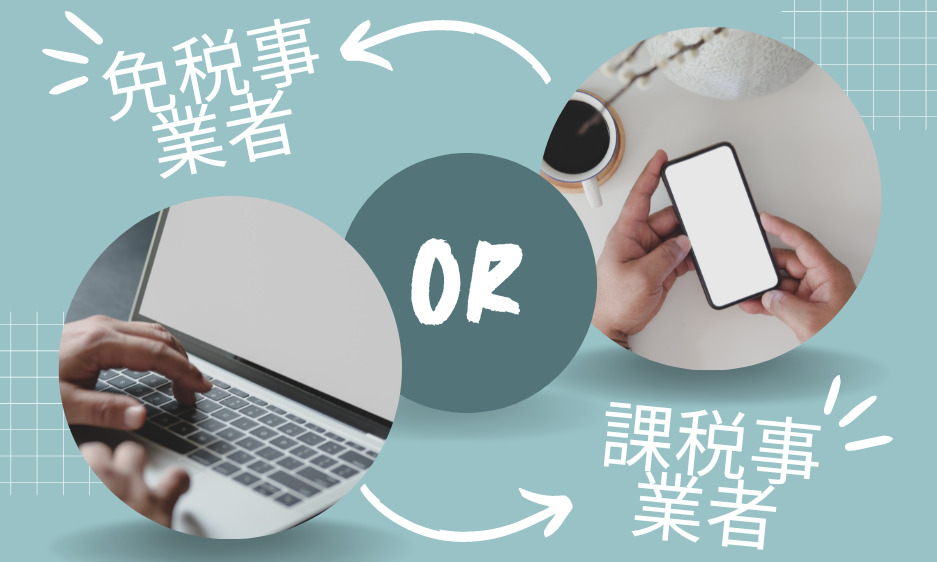 せどり業者は商品を免税事業者と課税事業者から購入することがありますが、インボイス制度の導入により、免税事業者から仕入れることは負担が大きい可能性が考えられます。
せどり業者は商品を免税事業者と課税事業者から購入することがありますが、インボイス制度の導入により、免税事業者から仕入れることは負担が大きい可能性が考えられます。
そのため、免税事業者は課税事業者になるか、またはインボイスを発行できるように登録する必要があるかもしれません。
免税事業者が課税事業者になる手続きをするには課税売上が1000万円を超える場合に課税事業者になりますが、課税事業者になることで消費税の還付を受けることができます。
課税事業者になるための手続きは税務署に提出する必要があります。
インボイス制度の開始により、せどり業者は仕入れ方法によって消費税の負担が変わってきます。
個人がフリマサイト経由で仕入れる場合はインボイス発行事業者からの仕入れは少ないことが予想され、適格請求書の発行を受けることが難しいでしょう。
また、ECサイトに出品している事業者は免税事業者か課税事業者かによっても異なります。
ですから免税事業者のせどり業者にとっては重要な選択を迫られることになります。
免税事業者のせどり業者に求められる選択
インボイス制度導入後、免税事業者のせどり業者は以下の選択を考えなければなりません。
- 売値を下げる
免税事業者であるせどり業者は、これまでに比べて商品を購入する際に免税出来なくなる可能性があります。
なので売値を下げることで税負担を軽減し、競争力を保つことが求められます。 - 課税事業者に変更する
免税事業者から課税事業者になることを選択するという手段もあります。
課税事業者になることで、消費税をダブルで納税するリスクを回避できます。 - インボイス発行業者に登録する
免税事業者のせどり業者は、インボイス制度を適切に運用するためにはインボイス発行業者に登録する必要があります。
しかし、登録することで手続きや負担が増える可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。
これらの選択肢の中から、免税事業者のせどり業者は自身の事業戦略や経済的な考慮などを考えながら最適な選択をする必要があります。
適切な対応をすることで新たなビジネスチャンスを見出すこともできるでしょう。
インボイスなしでも控除は可能!
ここまでインボイスがないと控除が認められないと説明してきましたが、例外もあります。
一般の消費者から仕入れる場合はインボイスが発行できないので、そのための対応策が存在するのです。
ただし、「古物営業法上の許可」をとっていることが条件になります。
まずは自分が特例の対象者であるかをしっかり確認してください。
インボイス制度には「古物商・質屋特例」というものがあり、「古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる」とされています。
特例を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。
(参照:インボイス制度における「古物商特例」の4つのポイント)
- 古物商又は質屋であること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
また、帳簿の記載ルールとして以下のような項目が挙げられています。
こちらを守っていないと特例が適用されないので注意しましょう。
- 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 取引年月日
- 取引内容(軽減対象である場合その旨)
- 支払対価の額
- 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
このように、課税事業者にならなくても「古物商」として登録がある場合は、インボイスなしでも控除を受けられます。
既に古物商登録をしているせどり事業者の方は、仕入れ時の注意点や帳簿の記載ルールに気をつけるようにしてください。
インボイス制度のせどりへの影響
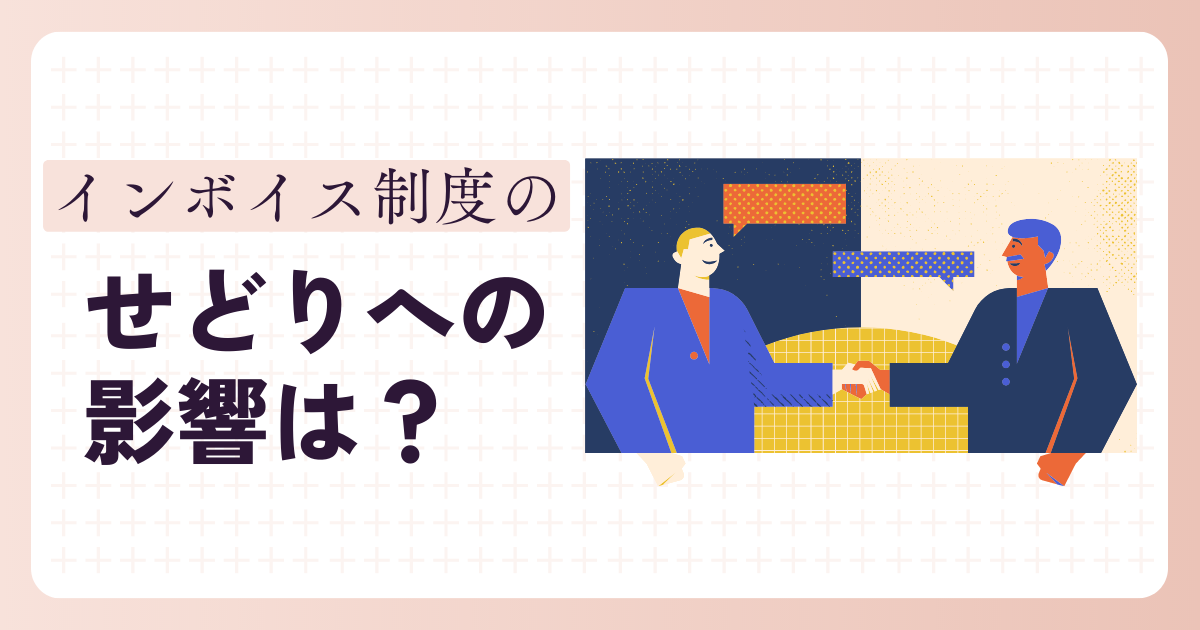 インボイス制度の始まりにより、せどり業界にはいくつかの影響が出ています。
インボイス制度の始まりにより、せどり業界にはいくつかの影響が出ています。
以下にまとめますね。
| ケース | 影響 |
|---|---|
| せどり業者が課税事業者で、適格請求書を所得できる場合 | 仕入に掛かった消費税を控除できるため、納税額が変動する |
| せどり業者が課税事業者で、仕入先がインボイス未登録の場合 | 適格請求書を発行できず、仕入に掛かった消費税を控除できないため、納税額が増加する |
| せどり業者が免税事業者で、仕入先が課税事業者の場合 | 仕入に掛かった消費税を控除できず、利益が減少する可能性がある |
| せどり業者が免税事業者で、仕入先がインボイス未登録の場合 | 免税事業者からの仕入では消費税を控除できず、利益が減少する可能性がある |
上記のケースごとに、インボイス制度が与える影響が違ってきます。
具体的には、課税事業者の場合、適格請求書の発行を通じて消費税の控除が可能かどうかが納税額に影響を与えます。
また、免税事業者だと、インボイス未登録の課税事業者や免税事業者からの仕入れにの場合に消費税の控除ができないため、利益が減少する可能性があります。
まとめ
さて、ここまでインボイス制度についてご紹介してきました。
この記事をまとめると以下の通り。
- 2023年10月から「インボイス制度」が始まる
- インボイス制度がはじまることによって、消費税の仕入税額控除申請の際にインボイス(適格請求書)という書類が必要となる
- 免税事業者だとインボイスが発行できないため、インボイス(適格請求書)を発行出来る事業者(課税事業者)でない場合は取引を断られるおそれがある
- 免税事業者を仕入れに利用している場合は、取引先に対応を求めたり、取引先の変更などを検討する必要がある
- インボイス制度には「古物商・質屋特例」があり、古物商登録をしている事業者なら一定の条件をクリアすることでインボイスなしで消費税の仕入税額控除申請ができる
インボイス制度は、せどり業界にとって大きな変化をもたらすことが予想されています。
特に、免税事業者にとってっは取引先の減少や売上の減少が生じる可能性があります。
仕入れ先・販売先の状況をしっかり確認して、インボイス制度の悪影響を受けることがないようにしっかり備えましょう。
 佐野
佐野初年度から万全の体制でインボイス制度に対応することで、影響を最小限に抑えることが重要ですね。
【毎月2名限定】無料面談のお知らせ
無料相談では、あなたがアマゾン販売で、
副収入を月10万円得るための方法や思考法をお伝えします。
また、個人事業主では、月30万円達成するための仕入れ先、
仕入れ方法を答えられる範囲で質問に回答させていただきます。
あなたの転売ビジネスを軌道に乗せる各種ノウハウはもちろんのこと
あなたが、立ち止まっている原因を解決していくこともできます。
但し、適性を見るために、面談前に、事前
アンケートも実施させて頂きますので、ご了承下さい。
【日時・締切日】
毎月第2日曜日:13時~14時
毎月第3日曜日:13時~14時
※コンサル生は、定員になり次第、一切募集を行いません
【面談形態】Skype or 電話
【参加料金】完全無料
【参加条件】テキスト審査に通過した方
【毎月2名限定】無料面談のお知らせ
無料相談では、あなたがアマゾン販売で、
副収入を月10万円得るための方法や思考法をお伝えします。
また、個人事業主では、月30万円達成するための仕入れ先、
仕入れ方法を答えられる範囲で質問に回答させていただきます。
あなたの転売ビジネスを軌道に乗せる各種ノウハウはもちろんのこと
あなたが、立ち止まっている原因を解決していくこともできます。
但し、適性を見るために、面談前に、事前
アンケートも実施させて頂きますので、ご了承下さい。
【日時・締切日】
毎月第2日曜日:13時~14時
毎月第3日曜日:13時~14時
※コンサル生は、定員になり次第、一切募集を行いません
【面談形態】Skype or 電話
【参加料金】完全無料
【参加条件】テキスト審査に通過した方

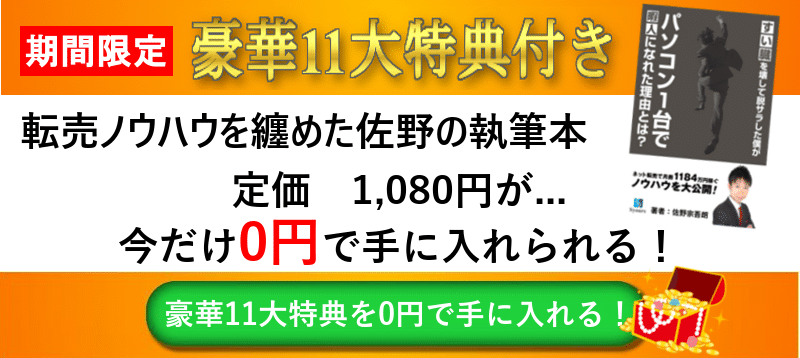
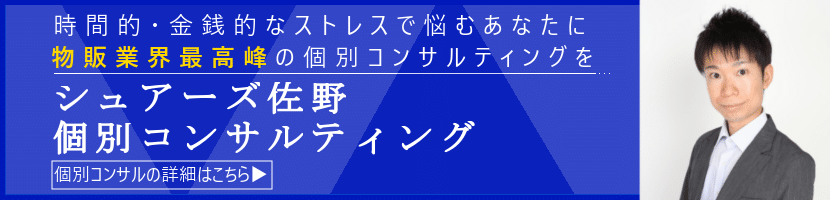
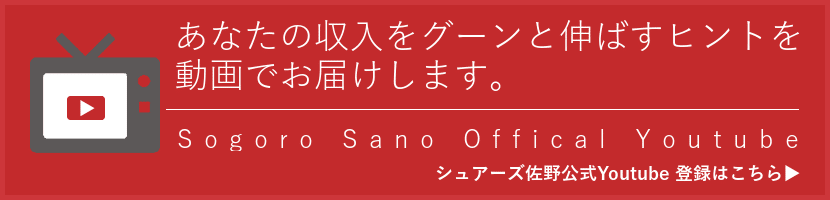
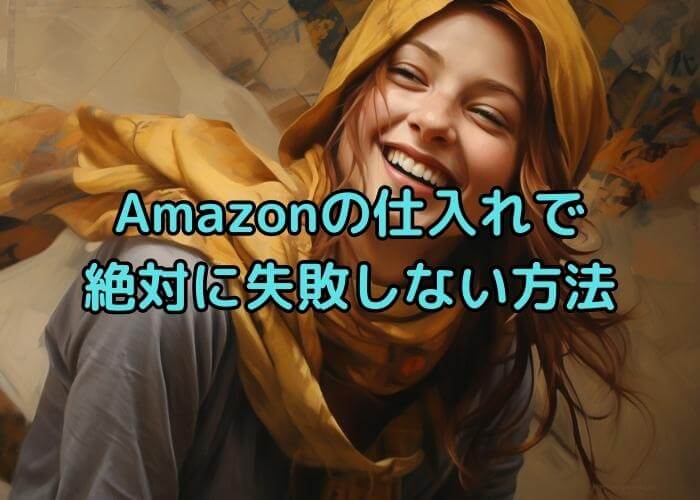



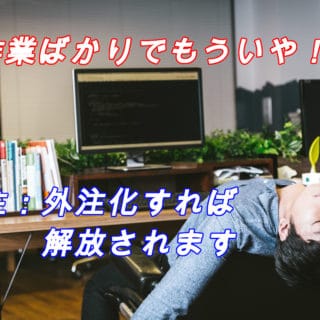
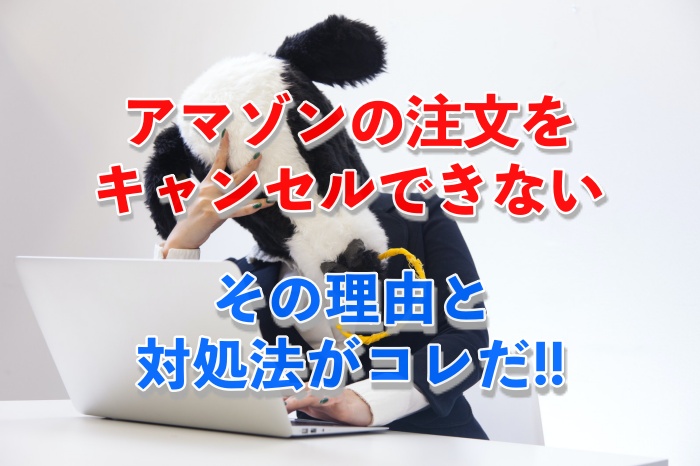
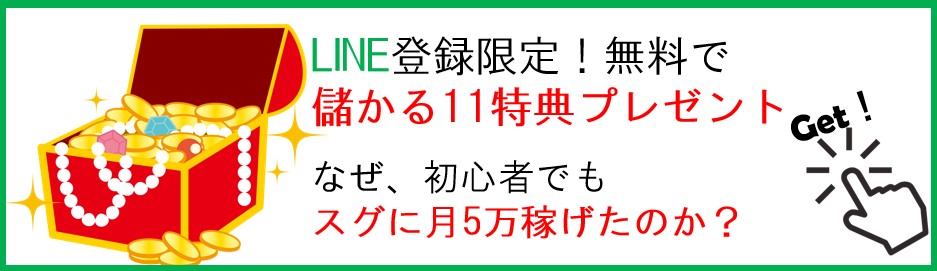

今なら11個の豪華特典を無料でプレゼント中
お忘れなくご登録ください!
毎月1名限定のコンサルティングはお早めにどうぞ!